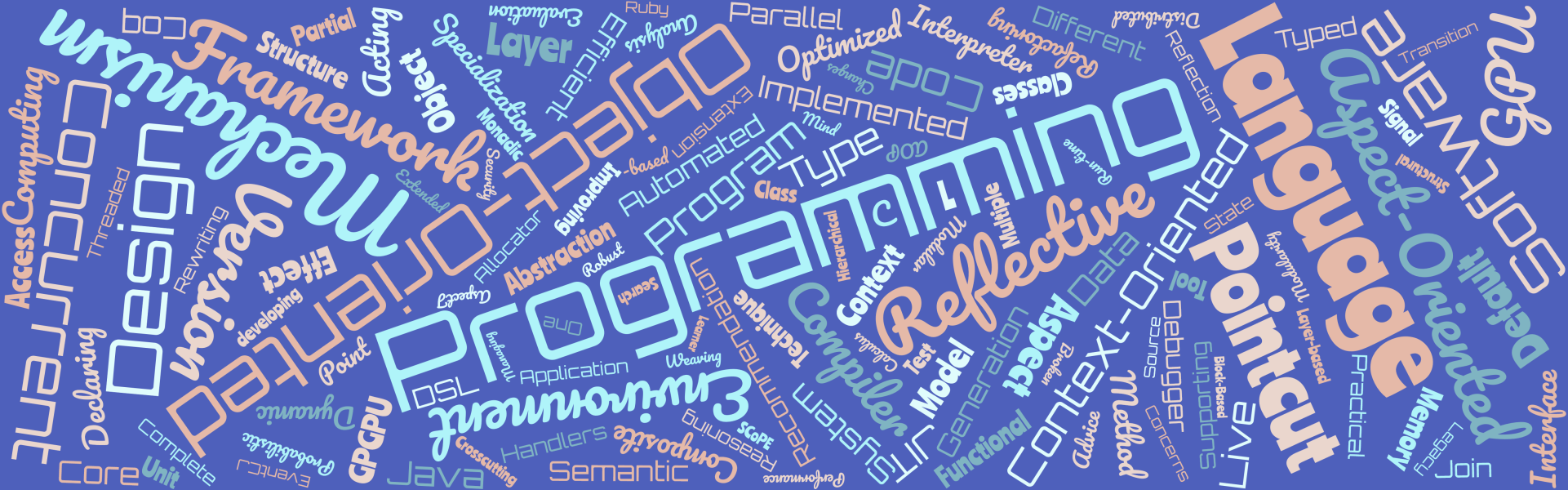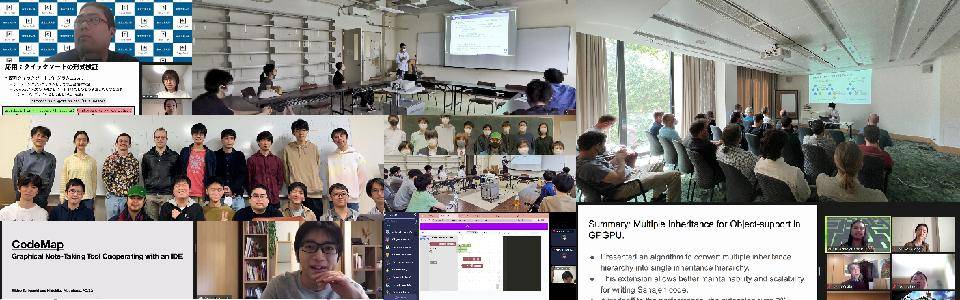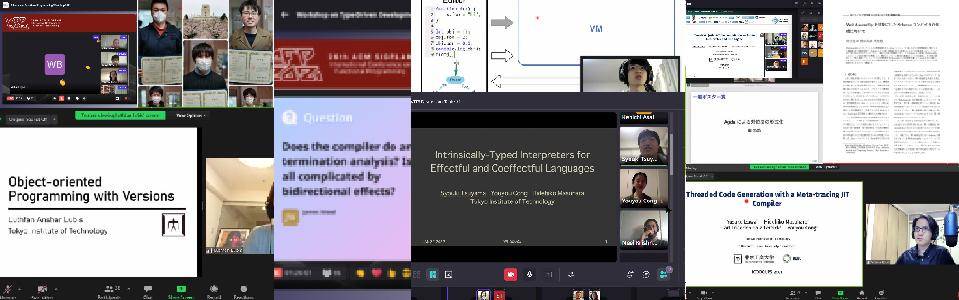わたしたちはプログラミング言語とソフトウェア開発環境を研究しています。プログラミング言語と環境の理論・設計・実現方式を追求することで「プログミングをもっと楽しく」することが研究室の大きな目標です。主な研究テーマには次のものがあります。
- プログラムを安全に書きやすくするためのプログラミング言語の理論、設計、実現方式。例えば型システム、制御機構、モジュール機構、プログラム合成技術などについての研究をしています。
- 効率の良いプログラムをより簡単に記述するためのプログラミング言語とその最適化手法。例えばGPGPU向けのプログラミング言語、実行時コンパイル技法、プログラム変換技術などについて研究しています。
- 統合開発環境のようなソフトウェア開発環境の、プログラミング言語技術や機械学習技術を用いた高度化。例えばライブプログラミング環境、教育用開発環境、コード補完、デバッガなどについて研究しています。
これらに限らず、プログラミング言語とソフトウェア開発環境に関する色々な研究を行っています。詳しくは研究プロジェクトのページをごらん下さい。この分野に興味を持つ学生・研究者を歓迎しています。
伊澤、増原、Bolzによる論文 “A Lightweight Method for Generating Multi-Tier JIT Compilation Virtual Machine in a Meta-Tracing Compiler Framework” が ECOOP 2025 に採択されました。6月30日からノルウェー・ベルゲンで開催される会議にて発表されます。この論文は伊澤の博士論文とその後の発展に基づく成果をまとめたものです。
(さらに…)
6月18日-19日にお茶の水女子大学で開催される Workshop on Metaprogramming and Related Topics 2025 で、3名のメンバーが発表を行います。
- 吉村友成: トレーシングJITコンパイラは多段階計算を救えるか?
- 陳智騏: Towards Programming with Effect Handlers and Typed Holes
- 叢悠悠: A Design Recipe for Algebraic Effects and Handlers
松山が関数型まつりで「Effectの双対、Coeffect」というタイトルの講演を行います。

ソフトウェア発展のための分散・永続プログラミングに関する2編の論文が<Programming>論文誌に採録されます。論文はまた2025年6月にプラハで開催される<Programming>国際会議でも発表されます。これらの論文は大分大学の紙名博士と山口東京理科大学の青谷博士との共同研究です。
(さらに…)
木内・田邉・増原による論文「Fork-Joinモデルで記述された細粒度並列プログラムのGPU上での効率的な実行手法の提案」が情報処理学会論文誌プログラミング に採録されることが決まりました。
この論文は2025年3月に行われた情報処理学会第153回プログラミング研究発表会でも発表されています。
(さらに…)
4月25日に、Hasso Plattner Institute のソフトウェアアーキテクチャグループのメンバー5名が研究室を訪問し、Tom Beckmann が “Defeating Dragons in the Classroom: Roleplaying Games for Teaching Communication Skills in Software Engineering” というタイトルの講演を行いました。

新たに加わった卒業研究学生2名と修士課程学生1名とともに、2025年度が始まりました。
👉構成員
2025年3月26日に学位授与式が行われ、木内・酒井が修士号を、稲葉・林・吉尾・熊本・小西・松山が学士号を授与されました。

 木内が東京大学駒場キャンパスにおいて開催された情報処理学会 第153回プログラミング研究発表会においてGPU上で細粒度スレッド実行を行う研究について発表しました。
木内が東京大学駒場キャンパスにおいて開催された情報処理学会 第153回プログラミング研究発表会においてGPU上で細粒度スレッド実行を行う研究について発表しました。
(さらに…)
松下祐介氏が PPL 2025 での以下のポスター発表に関して、ポスター賞(一般の部)を受賞しました。本ポスターは田邉助教との共同研究です。

👉ポスター
👉研究プロジェクト
(さらに…)